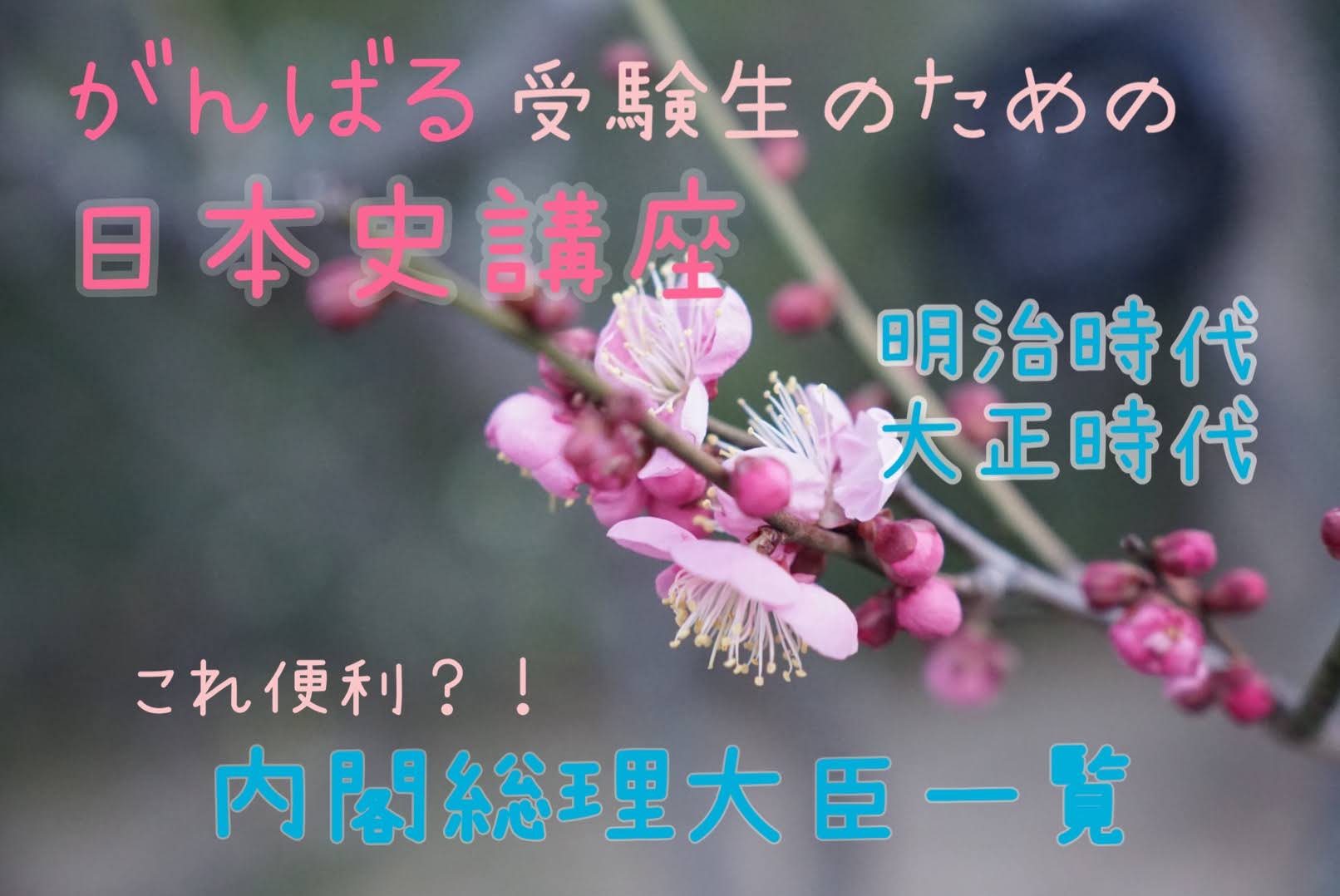明治時代~大正時代。覚える言葉も多く、困ったのが「内閣総理大臣」という方いませんか?なんと、現職の岸田総理が100代目。のべ100人も記憶するなんてそんな…。そこで、困っている受験生、そして、もう一回学びたい大人の方向けに新しい企画を始動! 歴史解説に必要なツールを投稿しようと思います。
その第一弾が、明治・大正時代の内閣総理大臣一覧です。
実際は、スプレッドシートに記入しており、100代全部記入が完了したら掲載も考えています。
今回は明治~大正時代について紹介します。
明治時代の内閣総理大臣
内閣制度が始まった!そもそも、日本には「天皇」「幕府」という組織があり、時代に応じてその政治の権力構造は変化しています。内閣がなぜできたかという理由は諸説ありますが、「天皇」が一番上であるというタテマエがあったその上で、「薩長土肥」勢力が政治的に実権を握るためとも言われています。
※薩長土肥…江戸~明治初期まであった、旧国(藩)の中でも、江戸幕府には反対の意思をもって「新体制へすすめようとした」4つの藩をさします。薩摩…鹿児島。長州…山口。土佐…高知。肥前…佐賀。

【ポイント解説(明治時代)】
① 伊藤博文など、複数回内閣総理大臣をしている人がいるので要注意。
② 在職期間については、明治~昭和、平成を通じて一番長い総理大臣を知ると便利。
1位…安倍晋三 3188日 2位…桂太郎 2886日 3位…佐藤栄作 2798日
桂太郎の期間については、日露戦争・ポーツマス条約の時期と重なっています。そして、西園寺公望と交互に総理大臣となっている「桂園時代」があったことは特徴的です。桂太郎は「陸軍大臣」。日露戦争時期に総理大臣をしている理由としても、記憶しやすいのではないでしょうか?
③ 使い方…歴史を勉強していて、重要事項の並べ替えで困る学生さんが多い印象も。その時は、上記表の「在職期間」を活用!
例:1894年は日清戦争→表の西暦をみると伊藤博文の時。
例:1904年は日露戦争→表から、桂太郎。
→どちらも、中国やロシアに勝っていて賠償金の請求もしていて順番を間違えがち。「伊藤博文は最初の内閣総理大臣」ということは有名。この情報も入れることで…並び替えも間違えないはず!
解説動画
大正時代の総理大臣

こちら大正時代。
【ポイント解説(大正時代)】
① 暗記本で発生する誤解対策に使おう!~1918年の米騒動について~
寺内正毅内閣時には、1918年米騒動が起こります。米騒動の年号を覚えるために、語呂合わせで、有名な原敬(はらたかし)と組み合わせて「ぴんくいや(1918)がる原敬」となっている本もあります。
しかし、実際に米騒動の発生は原敬の就任の前。つまり、原敬は事後処理として関わっています。
② 加藤高明内閣時、1925年の「普通選挙法」では、ついに納税金額の定めがなくなって、貧乏な人も選挙で投票できるようになりました。しかし、同時制定の「治安維持法」で、いわゆる「国家」に反抗的な態度を示すとされた「社会主義」に関する動きは封じることが可能になってしまいました。
明治・大正時代は政治面でも大きな動きを見せています。その中で「内閣総理大臣」は受験でもでてくるので要注意。知っておくと得なことも多くあります。
昭和時代になると、第二次世界大戦も始まり、軍部の総理大臣が就任していますし、犬養毅など有名な総理大臣も登場!いわゆる「憲政の常道」は昭和初期です。